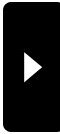2014年03月03日
30年前の大島青松園 2(強制隔離政策)
強制隔離政策
偽名
ハンセン病は容姿の問題から、日本では天刑病・業病などと呼ばれ、差別の対象になっていました
発症者が出ると、行方不明や死んだ事にして、地元を離れ、お遍路さんや、放浪して物貰いとなったりしていました、
ただし、遺伝病と考えられていたので、地域によっては、ひっそりと自宅療養している方も大勢おられたようです
放浪の際、家族、親類に危害が及ばぬ様に、偽名を使うのが一般的でした
略年表
1873年(明治6年)
ノルウェーのハンセンが、らい菌を発見
1897年(明治30年)
徴兵検査時に、この病気の有無を調べ始める (40万人から620人発見)
ベルリンで第1回国際らい会議が開かれ、伝染性疾患であることが国際的に確認され、隔離の必要性が提唱された
1902年(明治35年)
群馬県選出の代議士が外国人を華厳の滝に案内した際、患者が群がって物乞いしているのに出会い、恥をかいた為、
「らい患者取締に関する建議案」を帝国議会に提出、衆院承認も会期切れで不成立
1906年(明治39年)
らい予防法案提出 衆院は前回一致で可決したが貴族院は賛成せず不成立
同年イギリス大使館前で、放浪患者が行き倒れ。
大使が外務省にかけつけ「一等国日本に国の施設もないのか」となじる。
政府の施設推進のきっかけとなる
このころ、政府が起草中の法案内容を知った神山復生病院長ベルトラインが
「世界各国とも療養所を島や遠隔地に設けて成功したことがない。人道的にも好ましくない。都市近郊に設けよ」と進言するが、法案には反映されず
1907年(明治40年)
政府は「らい予防に関する件」を帝国議会に提案・可決される 旧らい予防法成立
1909年(明治42年)
旧らい予防法施行
明治政府が療養所を建てた背景
1 先進国としての対面
日露戦争(1904年~1905年・明治37・38年)に勝った日本は先進国の仲間入りを果たしたが、外人宣教師に頼ってばかり(私立の療養所を開設していた)では面目が立たないと考えるようになったのと、前述のイギリス大使館の強い勧告もあったため
2 軍事経済力への影響
明治30年から徴兵検査に、この病気の有無も調べ始めたが、同年検査した40万人から620人もの患者が発見された。650人に一人の割合
秘密にしている者、放浪者を考えると「今後100万人が罹患する恐れがある」といわれ、この病気は富国強兵への脅威だった
3 治安対策
各地に患者の集落(患者だけでは無い)ができ、とばく、詐欺、盗み、恐喝、殺人などの悪のルツボの観があった
4 明治30年の第1回国際らい会議で「伝染病と隔離の必要性が、科学的に確認された」こと
先進国の仲間入り、という肩書きの為に
「都合の悪いことは、目に付かなくしてしまおう」
という政策でした
療養所のできた1909年(明治42年)から1930年(昭和5年)にかけては、浮浪患者の収容が中心でしたが、入所条件が非常に厳しく、有料だった為、資産、扶養義務者調査で故郷に秘密が漏れるのを恐れて、入所希望者は少なく、そればかりか、いったん入所しても、逃走する者が多く、定員割れしていました
無らい県運動
国は、この病気の撲滅の為には、「在宅患者も強制収容するしかない」と考え
1929年(昭和4年)
無らい県運動広がる
根絶の為、一人残らず収容し(無らい)一人も患者がいない県にしようという運動です
1931年(昭和6年)
旧らい予防法が改正(改悪)され、それまでの有料制を廃し、全面的に公費負担の無料入所制となり、本籍・氏名を申告する必要もなくし、強制収用の法的根拠としました
無らい県運動を強力に後押しします
療養所の医師や県の職員が各地で講演。この病気の恐ろしさを説いて回りました。しかしそれは撲滅の必要性を強調するあまり、伝染力を誇大に宣伝することになり、民衆の恐怖心、偏見をいっそう煽り立ててしまいました
この病気が遺伝と思われていた時代には、地域共同体の人達も、患者やその家族を露骨に排斥するようなことはありませんでした。なぜなら、遺伝である以上自分達とは何の関係も無く、結婚の際に差別する程度だったそうです
しかし無らい県運動で、この病気は、あたかもその頃流行していたペスト並みの急性伝染病であるかのように宣伝された為、地域共同体の人達は、伝染を恐れ、患者とその家族を、地域から追い出しにかかりました。
患者さんと家族、親族の受難の時代が始まります
患者が見つかると、有無を言わさず保健所が、消毒に来る為、地域にばれてしまい、村八分や、一家離散・一家心中等、悲しい事が起こりました
又、療養所の定員をはるかに超える患者さんが送られ、療養所とは名ばかりで、大部屋にすし詰め状態で押し込まれ、職員不足の為、患者作業と言って、軽症者が重症者の世話をしたり、本来職員・看護師が行なう作業を、なかば強引にさせられました
外出も禁止され、療養所の指図に従わないと、療養所内の監獄に入れられたりしました
1941年(昭和16年)
アメリカで特効薬プロミン開発
1947年(昭和22年)
プロミンの使用開始
不治の病から可治の病へ
1953年(昭和28年)
らい予防改正法案可決
革新系国会議員が、全患協(全国ハンセン氏病患者協議会)の要請に応えて議員立法で改正しようとしたが、議員立法では面目が立たない為、あわてて厚生省が、旧法とまったく同じと言ってよい”改正案”を抜き打ち的に国会に提案。全患協は、延べ数百人の国会前座り込みやハンストなどで全力で反対したが、原案通りに成立。しかし抗議行動の結果、九項目の付帯決議を勝ち取りました
付帯決議のお陰で、待遇が改善されました
1956年(昭和31年)
「らい患者の救済と社会復帰のための国際会議」が、行なわれ全ての差別的法律の撤廃、在宅医療の推進、早期治療の必要性、社会復帰援助等をうたったローマ宣言が採択されました。
その中で日本の隔離主義が批判の対象となりましたが、政府が法律を改めることは、ありませんでした
(特効薬のお陰で、ほとんどの入園者が無菌状態で、隔離の必要性はすでにありませんでした)
永い時を経て・・・
1996年(平成8年)
らい予防法全廃
強制隔離政策のため、世間から忘れ去られたままになってしまいました。その為正しい啓蒙がなされておらず、今でも差別と偏見が残ったままです
今まで述べて来たことは、「厚生省の歴史から学ぶハンセン病」や「「国立ハンセン病資料館」の「ハンセン病資料館キッズコーナー」
で、とても分かりや易く解説していますので、目を通してみて下さい
その3へ続きます
園内散策の続きです(30年前の写真です)
地図を見ながら、説明していきます

桟橋から北へ向かい大島会館の前を過ぎると、宗教坂と呼んでいるこの坂があり、ここを登ると各宗教施設が集結している地域があります
ちょうどお盆の飾りつけの行灯が飾られています

坂を登りしばらく行くと、木立の中に1936年に建てられた初代の納骨堂が、ひっそりたたずんでいます

その先に?(この辺の記憶があいまいですが)、火葬場があります


島の北側を「北海道」と呼んでいました。ぐるりと廻れる「相愛の道」と名づけられた散策路が作られています
突端から振り返って、東の浜を眺めた様子です
並んで見える瓦屋根の建物が、入園者の居室です


宗教坂の一体には、「四国八十八ヶ所」を模した、お地蔵様が並んで居られます


宗教坂の東の斜面下には、防空壕があり、夏は涼しいので、畑で取れたスイカが冷やしてありました

宗教坂の下を東に向かうと、スーパーと郵便局があります


郵便局前をさらに東へ行くと、メインストリートに当たります


この辺りに、各施設が密集しています
面会人宿泊所 現在は喫茶店「カフェ・シェル」になっています

福祉室

図書館

盲人福祉会館

老人福祉会館

協和会館

南へ向かうと、病棟があります
停まっている車は園内専用で、ナンバーがありません


園内のあちこちに、園内専用(構内)電話ボックスがあります
出掛けて(園内で)、具合が悪くなった時などに、この電話で連絡し、園内車で迎えに来てもらったりします

病棟から南に、向かうと入園者の居室があり、さらに進んで
園の一番南から、北に向かって、東の浜を望んだところです

その3に続きます
ハンセン病に関して詳しく知りたい方は「厚生省の歴史から学ぶハンセン病」や「国立ハンセン病資料館」の「ハンセン病資料館キッズコーナー」が判りやすく説明してい
「30年前の大島青松園1」
「30年前の大島青松園3」
2016年に大島青松園に訪問した時の記事はこちら
偽名
ハンセン病は容姿の問題から、日本では天刑病・業病などと呼ばれ、差別の対象になっていました
発症者が出ると、行方不明や死んだ事にして、地元を離れ、お遍路さんや、放浪して物貰いとなったりしていました、
ただし、遺伝病と考えられていたので、地域によっては、ひっそりと自宅療養している方も大勢おられたようです
放浪の際、家族、親類に危害が及ばぬ様に、偽名を使うのが一般的でした
略年表
1873年(明治6年)
ノルウェーのハンセンが、らい菌を発見
1897年(明治30年)
徴兵検査時に、この病気の有無を調べ始める (40万人から620人発見)
ベルリンで第1回国際らい会議が開かれ、伝染性疾患であることが国際的に確認され、隔離の必要性が提唱された
1902年(明治35年)
群馬県選出の代議士が外国人を華厳の滝に案内した際、患者が群がって物乞いしているのに出会い、恥をかいた為、
「らい患者取締に関する建議案」を帝国議会に提出、衆院承認も会期切れで不成立
1906年(明治39年)
らい予防法案提出 衆院は前回一致で可決したが貴族院は賛成せず不成立
同年イギリス大使館前で、放浪患者が行き倒れ。
大使が外務省にかけつけ「一等国日本に国の施設もないのか」となじる。
政府の施設推進のきっかけとなる
このころ、政府が起草中の法案内容を知った神山復生病院長ベルトラインが
「世界各国とも療養所を島や遠隔地に設けて成功したことがない。人道的にも好ましくない。都市近郊に設けよ」と進言するが、法案には反映されず
1907年(明治40年)
政府は「らい予防に関する件」を帝国議会に提案・可決される 旧らい予防法成立
1909年(明治42年)
旧らい予防法施行
明治政府が療養所を建てた背景
1 先進国としての対面
日露戦争(1904年~1905年・明治37・38年)に勝った日本は先進国の仲間入りを果たしたが、外人宣教師に頼ってばかり(私立の療養所を開設していた)では面目が立たないと考えるようになったのと、前述のイギリス大使館の強い勧告もあったため
2 軍事経済力への影響
明治30年から徴兵検査に、この病気の有無も調べ始めたが、同年検査した40万人から620人もの患者が発見された。650人に一人の割合
秘密にしている者、放浪者を考えると「今後100万人が罹患する恐れがある」といわれ、この病気は富国強兵への脅威だった
3 治安対策
各地に患者の集落(患者だけでは無い)ができ、とばく、詐欺、盗み、恐喝、殺人などの悪のルツボの観があった
4 明治30年の第1回国際らい会議で「伝染病と隔離の必要性が、科学的に確認された」こと
先進国の仲間入り、という肩書きの為に
「都合の悪いことは、目に付かなくしてしまおう」
という政策でした
療養所のできた1909年(明治42年)から1930年(昭和5年)にかけては、浮浪患者の収容が中心でしたが、入所条件が非常に厳しく、有料だった為、資産、扶養義務者調査で故郷に秘密が漏れるのを恐れて、入所希望者は少なく、そればかりか、いったん入所しても、逃走する者が多く、定員割れしていました
無らい県運動
国は、この病気の撲滅の為には、「在宅患者も強制収容するしかない」と考え
1929年(昭和4年)
無らい県運動広がる
根絶の為、一人残らず収容し(無らい)一人も患者がいない県にしようという運動です
1931年(昭和6年)
旧らい予防法が改正(改悪)され、それまでの有料制を廃し、全面的に公費負担の無料入所制となり、本籍・氏名を申告する必要もなくし、強制収用の法的根拠としました
無らい県運動を強力に後押しします
療養所の医師や県の職員が各地で講演。この病気の恐ろしさを説いて回りました。しかしそれは撲滅の必要性を強調するあまり、伝染力を誇大に宣伝することになり、民衆の恐怖心、偏見をいっそう煽り立ててしまいました
この病気が遺伝と思われていた時代には、地域共同体の人達も、患者やその家族を露骨に排斥するようなことはありませんでした。なぜなら、遺伝である以上自分達とは何の関係も無く、結婚の際に差別する程度だったそうです
しかし無らい県運動で、この病気は、あたかもその頃流行していたペスト並みの急性伝染病であるかのように宣伝された為、地域共同体の人達は、伝染を恐れ、患者とその家族を、地域から追い出しにかかりました。
患者さんと家族、親族の受難の時代が始まります
患者が見つかると、有無を言わさず保健所が、消毒に来る為、地域にばれてしまい、村八分や、一家離散・一家心中等、悲しい事が起こりました
又、療養所の定員をはるかに超える患者さんが送られ、療養所とは名ばかりで、大部屋にすし詰め状態で押し込まれ、職員不足の為、患者作業と言って、軽症者が重症者の世話をしたり、本来職員・看護師が行なう作業を、なかば強引にさせられました
外出も禁止され、療養所の指図に従わないと、療養所内の監獄に入れられたりしました
1941年(昭和16年)
アメリカで特効薬プロミン開発
1947年(昭和22年)
プロミンの使用開始
不治の病から可治の病へ
1953年(昭和28年)
らい予防改正法案可決
革新系国会議員が、全患協(全国ハンセン氏病患者協議会)の要請に応えて議員立法で改正しようとしたが、議員立法では面目が立たない為、あわてて厚生省が、旧法とまったく同じと言ってよい”改正案”を抜き打ち的に国会に提案。全患協は、延べ数百人の国会前座り込みやハンストなどで全力で反対したが、原案通りに成立。しかし抗議行動の結果、九項目の付帯決議を勝ち取りました
付帯決議のお陰で、待遇が改善されました
1956年(昭和31年)
「らい患者の救済と社会復帰のための国際会議」が、行なわれ全ての差別的法律の撤廃、在宅医療の推進、早期治療の必要性、社会復帰援助等をうたったローマ宣言が採択されました。
その中で日本の隔離主義が批判の対象となりましたが、政府が法律を改めることは、ありませんでした
(特効薬のお陰で、ほとんどの入園者が無菌状態で、隔離の必要性はすでにありませんでした)
永い時を経て・・・
1996年(平成8年)
らい予防法全廃
強制隔離政策のため、世間から忘れ去られたままになってしまいました。その為正しい啓蒙がなされておらず、今でも差別と偏見が残ったままです
今まで述べて来たことは、「厚生省の歴史から学ぶハンセン病」や「「国立ハンセン病資料館」の「ハンセン病資料館キッズコーナー」
で、とても分かりや易く解説していますので、目を通してみて下さい
その3へ続きます
園内散策の続きです(30年前の写真です)
地図を見ながら、説明していきます

桟橋から北へ向かい大島会館の前を過ぎると、宗教坂と呼んでいるこの坂があり、ここを登ると各宗教施設が集結している地域があります
ちょうどお盆の飾りつけの行灯が飾られています

坂を登りしばらく行くと、木立の中に1936年に建てられた初代の納骨堂が、ひっそりたたずんでいます

その先に?(この辺の記憶があいまいですが)、火葬場があります


島の北側を「北海道」と呼んでいました。ぐるりと廻れる「相愛の道」と名づけられた散策路が作られています
突端から振り返って、東の浜を眺めた様子です
並んで見える瓦屋根の建物が、入園者の居室です


宗教坂の一体には、「四国八十八ヶ所」を模した、お地蔵様が並んで居られます


宗教坂の東の斜面下には、防空壕があり、夏は涼しいので、畑で取れたスイカが冷やしてありました

宗教坂の下を東に向かうと、スーパーと郵便局があります


郵便局前をさらに東へ行くと、メインストリートに当たります


この辺りに、各施設が密集しています
面会人宿泊所 現在は喫茶店「カフェ・シェル」になっています

福祉室

図書館

盲人福祉会館

老人福祉会館

協和会館

南へ向かうと、病棟があります
停まっている車は園内専用で、ナンバーがありません


園内のあちこちに、園内専用(構内)電話ボックスがあります
出掛けて(園内で)、具合が悪くなった時などに、この電話で連絡し、園内車で迎えに来てもらったりします

病棟から南に、向かうと入園者の居室があり、さらに進んで
園の一番南から、北に向かって、東の浜を望んだところです

その3に続きます
ハンセン病に関して詳しく知りたい方は「厚生省の歴史から学ぶハンセン病」や「国立ハンセン病資料館」の「ハンセン病資料館キッズコーナー」が判りやすく説明してい
「30年前の大島青松園1」
「30年前の大島青松園3」
2016年に大島青松園に訪問した時の記事はこちら